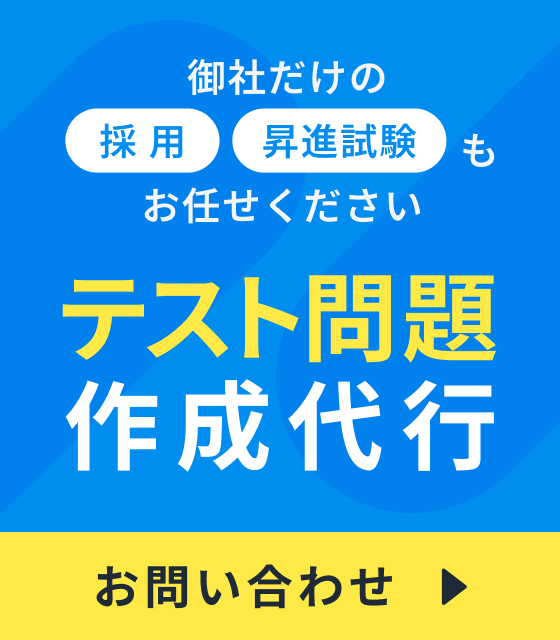採用の失敗やミスマッチが発生すると、成果を出してもらえないことはもちろん、周囲の雰囲気に悪影響を及ぼしたり、同じチームメンバーの業務負荷が高くなりすぎたりといった様々な問題につながります。
早期離職は採用や教育のコストが無駄になってしまうという意味でも会社に損害が発生することになります。エン・ジャパンの調査によると、社員1名が入社後3ヶ月以内に退職した場合の損失概算は187.5万円です。
ミスマッチが生じるのは、企業側、転職者の双方に原因があります。ただ、企業が転職者に責任を求めても何も改善できなくなるだけですので、選考時にきちんと見極めができなかった自らの責任だと考えて、どうすれば採用の失敗やミスマッチがなくなるのかを考えて取り組み続ける必要があります。
この記事では、採用における失敗やミスマッチを防ぐために取れる具体的なステップを紹介します。事前準備、採用選考、内定後のオンボーディングの3つのステップに分けて説明します。また、プロセスにおいて筆記試験がどのように役立つかも併せて解説します。
目次
そもそもミスマッチの原因は?
採用におけるミスマッチはなぜ発生するのでしょうか?以下要因ごとに解説します。
カルチャーの不一致を見抜けない
もっとも大きなミスマッチの原因は企業カルチャーと人材が噛み合わないことです。企業はそれぞれ独自の文化や価値観を持っており、社員の働き方やコミュニケーション方法、意思決定のプロセスに大きく影響します。
例えば、チームワークを重視する企業では個人プレーを好む人材は適応しにくいです。また、自由度の高い環境を求める人材が、何をするにも大人数による承認が必要な厳格な規律を重視する企業に入るとストレスを感じるでしょう。
スキルの不一致を見落としてしまう
採用された人材が求められるスキルセットを持っていない場合もミスマッチの大きな原因となります。具体的には、技術的なスキルや業務知識が不足している、または実務経験が不足している場合が該当します。これにより、業務のパフォーマンスが期待値に達せず、企業側も人材側も不満を抱くことになります。
スキルの不一致を避けるためには、まず自社の業務で求められるスキルを明確にする必要があります。たとえば、マーケティング担当者を募集するとしても、広告の出稿経験が豊富な方がよいのか、調査分析などのデータ取り扱いに優れた人がほしいのか、メディアの運用経験がある人など、細分化したときに特にどこのスキルが必要なのかを定義して、求人票に記載しましょう。
何ができれば必要十分なのかをしっかりと決めたあとは、選考過程で具体的なスキルチェックテストや実務シミュレーションを行うことが効果的です。
選考プロセスに問題がある
選考プロセス自体に問題がある場合も、ミスマッチが発生する要因の一つです。お互い腹を割って面接などで良いことだけではなく悪いことも含めて話し合えているかがミスマッチを減らすために大切なポイントです。会社の良い面だけを説明して、悪い面を隠していれば、入社直後にギャップを感じる人が増えてしまいます。
選考プロセスの途中で候補者の方に担っていただく役割や、期待している業務内容、アプトプットの水準などを正しく伝えておくこともミスマッチを減らすことに繋がります。
面接で必ずする質問や説明するべきことなどをドキュメント化して、面接官の対応がぶれることのようにします。面接官のトレーニングや評価基準の明確化、適切なアセスメントツールの導入もあわせて検討してください。
オンボーディングに問題がある
採用後のオンボーディングプロセスに問題があると、入社後のミスマッチが顕在化しやすくなります。新入社員が業務にスムーズに適応できるようにするためには、適切な研修プログラムやメンター制度の導入が重要です。
入社したばかりの人が早く成果を出せるように全員でサポートする文化になっているかはオンボーディングの正否に影響します。中途で経験豊富なメンバーが入社すると、お手並み拝見と周囲がまったくサポートしないということが起こります。これによって、入社したばかりのメンバーは、何をどう進めればよいかわからず成果を出せなくなり、居心地が悪くなって早期離職してしまいます。
入社初期のフィードバックを積極的に行い、問題点を早期に解決することも大切です。ミスマッチの状態を解消するために、フィードバックで直すべきポイントをきちんと伝え続けましょう。
以下はミスマッチを無くすための選考プロセスを説明しています。
事前準備
採用の理由・目的の検討
なぜ新しい人材を採用するのか、採用するポジションごとにその理由や目的を明確にします。これにより、採用活動の方向性が定まり、求める人材像が具体的になります。
直近で採用する人材像を定義するだけではなく、将来の組織図を書いてみて、今後採用する可能性がある職種(=役割)をリストアップしておくことを推奨します。たとえば1年後、3年後、5年後などそれぞれで売上・利益の規模や組織図などのイメージを作成しておくことで、採用活動を将来を見据えたものにできます。
採用する人材像を明確化して求人票に落とす
採用の理由と目的が明確になったら、次にどのような人材が必要かを具体的に定義します。ここでは、「求めるスキル」「必要な経験」「望ましい性格」などをリストアップし、ジョブディスクリプションを作成します。求人サイトなどに掲載する募集要項をできるだけ詳しく書いておくことで、求職者の方々との認識のズレが減り、ミスマッチが発生しにくくなります。
そんな人はいないのでは?という設定をしないように気をつけます。たとえば、すごく経験豊富で多くのことができる前提なのに給料は低い金額帯で設定しているなら、誰も応募してくれないです。
採用選考
適性検査や筆記試験の実施
適性検査や筆記試験を実施することで、候補者のスキルや適性を正確に評価することができます。これにより、実際の業務で求められる能力を持っているかどうかを見極めることができます。適性検査で性格的な傾向を見ることは、カルチャー面でのミスマッチを減らすことに効果的です。
一方で、スキルチェックを目的とした筆記試験は、技術的・専門的な知識の確認に効果的です。候補者のスキルや知識を評価するために役立ちます。特に専門知識が求められるポジションでは、事前に筆記試験を実施することで適性を見極めることができます。
たとえばエンジニア職で採用するときに、経験者ならプログラミングのスキルチェックテストを、未経験者でこれからエンジニアになる新卒向けには論理的思考能力、数的処理能力の筆記試験をするといったように、ポジションごとに異なる選考を実施できます。これにより、職務経歴書や履歴書の情報だとスキルがあるように見えたのに面接で話してみたらまったく専門的な話が通じなかったといった失敗を減らせます。
選考プロセス、面接回数の見直し
面接では、候補者の人間性や職場の文化との相性を見極めることが重要です。複数の面接官が参加し、様々な視点から評価することで、より客観的な判断が可能になります。採用の失敗を減らすためのコツは、面接に参加した誰かが少しでも懸念を感じた場合にお見送りすることです。何か違和感があったときに、まあいいかと目をつぶって採用することはミスマッチの原因になります。
書類選考と面接だけで採用している企業の場合、筆記試験やワークサンプルテストといったプロセスを入れることで、より正確に人材を見極めれるようになる可能性があります。ワークサンプルテストとは、ケーススタディーのような問題を出し、プレゼンテーションやレポートといった実務に近い形で回答してもらうものです。
企業文化の共有
候補者に企業文化や職場環境について詳しく伝えることで、ミスマッチのリスクを軽減できます。具体的なエピソードや社員の声を共有することが効果的です。
企業のミッション・ビジョン・バリューへの共感を確認するのも採用の失敗を減らすことにつながります。候補者の方が担当する予定の業務範囲を説明するだけではなく、会社全体として何のために、どういう方向に向かって事業をしているのかをしっかりと伝えます。
ネガティブ情報の提供
企業の弱点や課題も含めてオープンに伝えることが重要です。これにより、候補者が入社後に感じるギャップを減らすことができます。
平均的な残業時間や、異動や転勤の頻度など、仕事の大変な点や泥臭い部分も包み隠さずすべて伝えます。仕事内容が事前に聞いていたものと違うと入社直後に感じたなら、早期離職してしまう可能性は高くなるでしょう。
スペシャリストとして特定の領域を極めたいと考えている人に対して、ジョブディスクリプションと異なる業務についても広く担当してもらうようなことになるとミスマッチとなり離職につながります。たとえばスタートアップでは、誰もが広い業務範囲を柔軟に対応することが求められますので、成果を出すためには何でも必要に応じて担当するというマインドセットを持った人が望ましいです。事前に企業側から業務内容が頻繁に変わる可能性があると伝えておくことで、そうした働き方のスタイルを望まない人は入社しなくなるでしょう。
キャリアイメージのすりあわせ
入社後にどんな経験を積めると理想的なのか、将来どんな状態になっているのが理想なのかをヒアリングします。同じ役割の中でも、マネジメントを志向している人と、スペシャリストを志向している人で、理想的な働き方は違います。
たとえばエンジニアやデザイナーの方でスペシャリストを志向しているのに、部下をたくさんマネジメントするみたいな業務が割り当てられてしまえばミスマッチとなります。
懸念点のすり合わせと解消
内定を承諾してもらう前に、懸念点や気になることをできるだけ共有してもらい、解消するようにします。たとえば必要に応じて子育てすることになったときの時短勤務の利用状況、産休・育休や有給の取得状況などデータを共有します。
また面接では上長となる予定の管理職としか候補者の方が話していない場合、毎日やり取りすることになる同じ役割の人たちがどのような人たちなのか知りたいと考える人は多いです。選考のための面接とは別で、内定後に希望に応じて一緒に働くことになるメンバーと話す場を設けるのは有効です。
候補者の方の不安を解消するためにできることはすべて実施します。
内定後のオンボーディング
入社前のコミュニケーション
内定後も継続的にコミュニケーションを取り、候補者が不安や疑問を解消できるようサポートします。人事・総務から定期的に連絡を取ることはもちろん、一緒に働くことになる同じ部署の担当者と入社前の面談を実施することも有効です。
さらに、社内のマニュアル・議事録など各種ドキュメントをまとめているグループウェアのアクセス権限を渡したり、TeamsやSlackやチャットワークなどの社内コミュニケーションをとっているチャットの場などに招待することもおすすめです。やる気のある人は入社前に各種ドキュメントに目を通してくれますのでスムーズに勤務開始できます。
対応の漏れを無くすために、内定を出したあとに連絡する方法や伝えることを一通り整理してマニュアルやチェックリスト化しておくことがおすすめです。
キャリアパスの提示
内定者に対して明確なキャリアパスを提示することが重要です。内定者の希望を面談などでヒアリングしつつ、会社の目指すベクトルと、内定者がキャリアにおいて目指すベクトルのすり合わせをします。これにより、候補者は自分の成長のビジョンを描きやすくなります。
面談でフォローアップ
入社後のフォローアップも重要です。定期的な面談(1 on 1)を行い、社員が感じている課題や悩みを早期に把握し、適切なサポートを提供します。実務でやり取りする上長とは別に先輩社員をメンターとしてつけ、わからないことがあったときにすぐ質問や相談をできるようにしておくことも有効です。
教育研修
どう業務を進めるかの研修を通じて、新入社員がすぐに成果を出せるようにしてあげることが定着につながります。小さな成功を体験してもらう流れを作っておくことで早くチームに馴染めるようになります。異業種からの転職者や若手社員などはマニュアルを読み合わせするなどして、具体的な作業レベルまで落とし込んで説明していくのがおすすめです。
また、研修とあわせて、独自の筆記試験を実施することで、知識やスキルが身についているかを把握することも有効です。同じ教育研修を受けた人の中には、一度聞いただけですぐすべてを理解して実践できる人もいれば、一度では理解しきれずに業務中に混乱してしまう人もいます。理解度を確認することで先輩社員がフォローできるようになります。
社員同士のコミュニケーション促進
新入社員が既存社員とスムーズにコミュニケーションを取れるよう、イベントを実施します。たとえば、ランチをチームを横断して複数回行って、所属しているチーム以外の人間関係を構築できるようにします。これにより、新入社員が会社内をより広く知ることができますし、既存の従業員も新入社員の人柄や業務について知ることで協力しやすくなります。
適切な評価・人事制度の整備
公平で透明性の高い評価・人事制度を整備し、それを開示して伝えます。ただグループウェア上に公開しておくだけではなく、入社時のオリエンテーションなどで説明しておくことが望ましいです。どう評価されるのかがわからないまま働くのは、ルールがわからない状態でスポーツやゲームをしているような状態で、やる気の減退やストレスが増えることにつながります。
社員が納得感を持って働ける環境を作ります。これにより、評価や人事制度への不満を減らすことができます。
このように、選考プロセス開始前の準備から採用選考、そして入社後のオンボーディングに至るまで、各ステップでの工夫が採用の失敗やミスマッチの防止に繋がります。
一部のプロセスに筆記試験を適切に活用することで、候補者のスキルや適性を正確に評価し、入社後のミスマッチを減らすことができます。
ラクテスでは、サンプルテストを活用してオリジナルのテストを作ることができます。採用に筆記試験を導入される際にご活用ください。また、貴社向けのオリジナルのテストの作成を代行することも可能です。以下のページの下部にある「お問い合わせ・資料請求はこちら」からご連絡ください。
採用試験・テストの作成と運営を簡単に | ラクテス