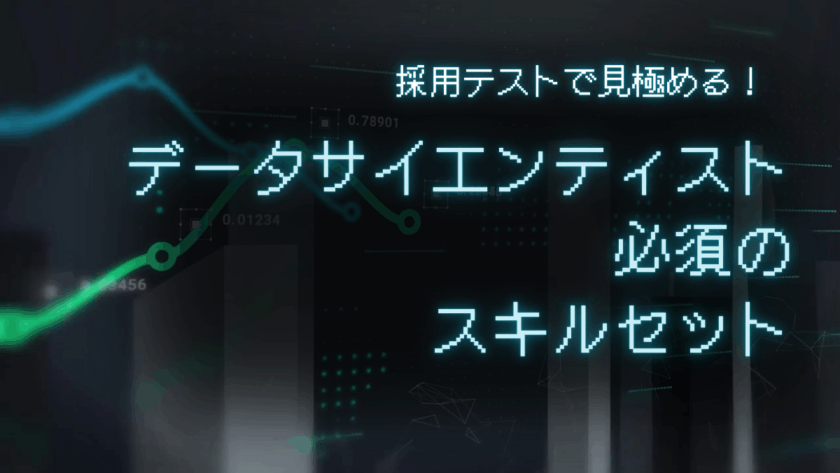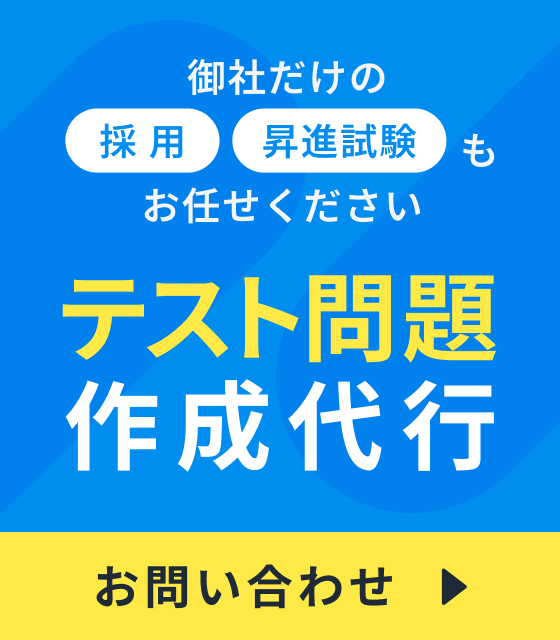データサイエンティストを採用するとき、「どのスキルを持っていれば成果につながるのか」という問いに直面します。
統計やプログラミングに詳しい人を採ったのに、事業貢献につながらなかったという失敗事例は少なくありません。逆に、スキルが完璧でなくても課題を正しく定義し、現場と協力して成果を出せる人材は大きな価値を生み出します。
本記事では、採用担当者が押さえておくべき「3つのスキルセット」と、それぞれをどのように評価すべきかを解説します。候補者が成果を出せる人材かどうか、本記事を参考に見極めましょう。
目次
データサイエンティストに必須の「3つのスキルセット」
データサイエンティストの仕事は一見すると高度な分析やモデル構築が中心に思われがちですが、実際には「どのように課題を設定するか」「どのようにデータを準備するか」といった基礎的な力が成果を左右します。
必要なのは「ビジネス力」「データサイエンス力」「データエンジニアリング力」の3つです。この3つをバランスよく持っていなければ、どんなに華やかなスキルを持っていても実務では結果を残せません。採用担当者は、この3つを基準に候補者を評価することが重要です。
1.ビジネス力=課題を定義し成果に結びつける力
ビジネス力は「データをどう使えば成果につながるか」を考え抜く力です。ただデータを集計するのではなく、「顧客属性や購買行動に基づいて分析し、改善策を提案する」レベルまで落とし込めるかがポイントです。課題を明確に定義できなければ、分析は自己満足で終わり、現場に受け入れられません。
さらに、経営層や現場担当者にわかりやすく説明する力も求められます。いくら正確な分析を行っても、意思決定者に理解されなければ実行に移せないからです。
面接では「あなたが過去に定義した課題と、その後の成果」を聞くと、この力を見抜きやすいでしょう。
2.データサイエンス力=統計や実験で検証する力
データサイエンス力とは、統計や機械学習を用いて仮説を検証する力です。単にモデルを作れるかではなく、「正しい実験設計ができるか」「妥当な評価指標を選べるか」が実務で大きな差を生みます。
たとえばA/Bテストを実施するときに、サンプル数をどのように設定するか、効果を測る指標は何にするかを論理的に説明できなければ、施策の信頼性は低下します。また、最新のアルゴリズムに詳しくても、再現性や透明性を欠いたモデルは現場で使えません。
採用担当者は「なぜその手法を選んだのかを説明できるか」を確認しましょう。候補者が専門知識を実務に応用する力を持っているかどうかが見えてきます。
3.データエンジニアリング力=データを整え運用する力
データエンジニアリング力とは、データを収集・加工し、利用可能な状態に整える力です。さらに、データ基盤を設計・運用し、継続的に改善していく力も含まれます。
欠損値、異常値、フォーマットの不一致などが放置されていると、いくら高度な分析をしても信頼できる結果は得られません。
この力を持つ人材は、単なる分析担当にとどまらず、組織全体のデータ活用を支える存在になります。採用時には「これまでどんなデータ基盤を整備したか」「本番運用における改善事例はあるか」を具体的に質問すると、候補者の実務能力を見極められます。
スキルセットが実践レベルか見極めるポイント6つ
候補者が「知識を持っている」だけでは、採用後に成果を出せるとは限りません。重要なのは、学んだことを実務で再現し、改善を繰り返せるかどうかです。
ここでは、面接や課題を通じて確認すべき6つの具体的な観点を紹介します。どれも実務に直結しており、これらのポイントを意識的にチェックすることで「期待外れの採用」になるリスクを低減できます。
1.データ取得能力があるか
データ活用の出発点は「必要なデータを正しく取り出せるか」です。SQLやAPIを使って自分でデータを引き出せる候補者は、現場での即戦力になります。一方で、知識だけで手を動かせない人材は、日常の分析業務すら滞ります。
面接では「過去にどのような方法でデータを取得したか」「困難なデータをどう取得したか」を具体的に尋ねると、実力を見極めやすくなります。
2.データ整理・前処理ができるか
どんなに高度なアルゴリズムも、前処理が不十分なデータでは役に立ちません。欠損値や外れ値の処理方法、フォーマットの揺れをどう扱うかは実務で頻繁に直面する課題です。これを雑に処理する人材は、結果を歪め、信頼性を損ないます。
候補者が「どのようにデータをクリーニングした経験があるか」を語れるかを確認することで、基礎力を確かめられます。
3.探索・可視化で仮説を立てられるか
探索的データ分析(EDA)や可視化は、単なる作業ではなく、問題解決の出発点です。優れたデータサイエンティストは、可視化の中から「筋の良い仮説」を導き出します。逆に、ただグラフを並べるだけでは「何を検証すべきか」が見えてきません。
面接や課題でサンプルデータを渡して、どんな仮説を立てるか尋ねてみると、候補者の思考力や直感の質がよくわかります。
4.実験設計と検証ができるか
施策の効果を検証するためには、正しい実験設計が不可欠です。サンプル数をどう決めるか、どんな評価指標を選ぶかを間違えると、プロジェクトは「やったけど意味がなかった」で終わります。特にPoC(概念実証)段階で止まってしまう企業は、この部分の見極めを軽視しがちです。
候補者には「過去に実施した実験設計とその成果」を具体的に説明させましょう。論理的な思考ができるかどうかが浮き彫りになります。
5.モデル構築・評価を説明できるか
モデルを構築するスキルはもちろん必要ですが、さらに大切なのは「なぜその手法を選んだのか」を説明できる力です。精度が高いモデルでも、説明できなければ現場や経営層の合意を得られません。逆に、シンプルなモデルでも説明力が高い候補者は、社内や関係者の信頼獲得がスムーズです。
採用担当者は「過去のモデル構築でどんな手法を選び、どんな基準で評価したか」を問いましょう。
6.運用・改善まで考えられるか
モデルの構築後、本番環境がスタートしてからの「見通しの深さ」も重要です。精度の劣化を監視し、必要に応じて再学習などの改善を続ける姿勢があるかどうかを見極めましょう。ここを軽視すると、「導入したが使われないモデル」になってしまいます。
候補者に「運用時にどんな改善を行ったか」を聞くことで、継続的に成果を出せる人材かどうかを判断できます。
データサイエンティストの採用で注意すべきこと
スキルセットを見極めるポイントを押さえても、採用全体の流れでつまずくことがあります。ここでは採用担当者が陥りやすい失敗と、それを避けるために必要な視点を解説します。
類似職種との違いを理解する
データサイエンティストは、しばしば他の類似職種と混同されます。役割を明確に区別せず採用すると、業務のミスマッチが起こり「期待した役割を果たせない」という問題につながります。採用担当者が各職種の違いを理解し、ポジションの要件を具体的に定義しておくことが欠かせません。
データアナリストとの違い
データアナリストは、主にデータの集計や分析結果の可視化、レポート作成を担います。課題の仮説立案や実験設計までは担当せず、意思決定への直接的な貢献は限定的です。
- データアナリスト:集計や分析結果をまとめ、レポートとして提供する役割。主に「過去や現状を可視化する」ことに強みがある。
- データサイエンティスト:データを基に仮説を立て、実験や検証を行い、意思決定に活かす役割。「未来を予測し、施策につなげる」点で異なる。
データエンジニアとの違い
データエンジニアは、データ基盤の設計や構築、パイプライン整備に特化しています。データを「使える状態」にすることが役割であり、課題定義や仮説検証までは担当しません。
- データエンジニア:データを収集・蓄積・加工し、分析可能な状態に整える。基盤やパイプライン構築など「土台作り」に特化。
- データサイエンティスト:その基盤を活用して、課題を検証し価値を生む。「整えたデータをどう活かすか」にフォーカスする。
機械学習エンジニアとの違い
機械学習エンジニアは、モデルの実装や本番運用を担う職種です。高度なプログラミング力やインフラ知識が求められますが、課題定義やビジネス課題との接続はデータサイエンティストの役割です。
- 機械学習エンジニア:アルゴリズムを実装し、本番環境に組み込み、モデルの最適化を行う。技術的な実装力が中心。
- データサイエンティスト:課題を定義し、どのモデルや手法を使うべきかを決める立場。仮説から施策提案までの広い視点を持つ。
面接で「3つの要点」を確認する
スキルセットの有無だけでなく、面接では「なぜそのスキルが成果につながるのか」を確かめることが重要です。課題定義力、説明力、運用視点の3つをセットで確認することで、採用後に失敗するリスクを大幅に減らせます。
課題をどう定義するか
課題を正しく整理できる候補者は、分析の方向性を誤りません。定義できない場合、PoCで止まって実務に活かせない可能性が高まります。
課題をわかりやすく説明できるか
分析の根拠や評価指標を説明できない人材は、社内合意を得られず施策が進みません。説明力は成果を現場に届けるための必須スキルです。
実際の運用まで考慮できるか
モデルの監視や改善を前提に話せる候補者は、長期的に成果を出せます。運用視点を欠いた採用は「作っただけで使われないモデル」を生みやすいため注意が必要です。
基礎テストで最低限のスキルを確認する
面接だけでは見抜けない基礎スキルは、短時間のテストで確かめるのが有効です。統計、SQL、Python、可視化などの共通基礎を測れば、候補者の実力を客観的に比較できます。テストを導入すれば、面接をスキル深掘りに集中でき、採用効率が上がります。
採用後はロードマップを用意する
採用で終わりではなく、入社後の育成計画を用意することで定着率と成果が高まります。90日でデータ品質改善と可視化、6か月で実験設計、12か月で本格的な運用改善に到達するロードマップを引けば、候補者は明確な目標を持って成長できます。採用担当者にとっても、組織としての投資対効果を測りやすくなります。
データサイエンティストのスキルセットを基準に採用と育成を一貫化する
データサイエンティスト採用の成否は、スキルセットの理解と見極め方にかかっています。「ビジネス力」「データサイエンス力」「データエンジニアリング力」の3つを軸に、実務レベルの6つの評価ポイントをチェックしましょう。
また、類似職種との違いを整理し、面接と基礎テストで適切に候補者を見極めれば、採用ミスを防げます。入社後のロードマップも作成すれば、事業に直結する成果を生み出すデータサイエンティストを育てられます。
なお、ラクテスではデータサイエンティスト向けのスキルチェックテストを提供しています。データサイエンティストに必要なスキルをまとめて測れるため、ぜひ採用候補者や育成人材の現状把握にご活用ください。
データサイエンティストのスキルセットを測定する問題【採用・研修用】
他にも、ラクテスにはデータサイエンティストの採用に役立つテストを多数ご用意しています。あわせてご覧ください。