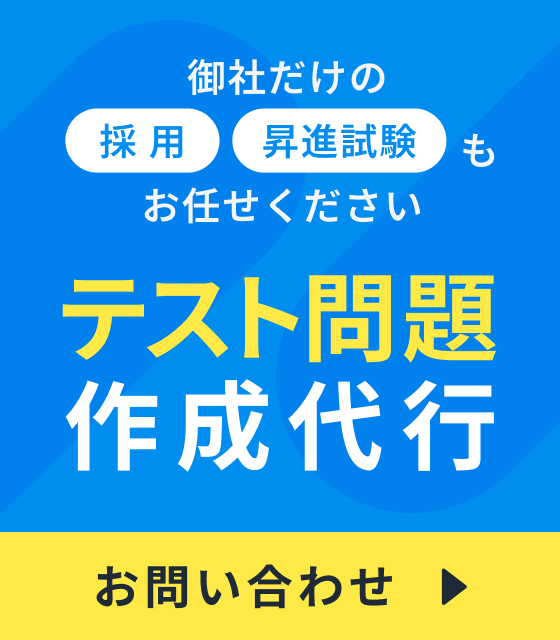従業員の定着率を上げるには、まず「なぜ人が辞めるのか」を把握し、その原因を解消し続けることが欠かせません。とりわけ中小・中堅企業では一人の役割が大きく、誰かが辞めると業務や社内の雰囲気に大きな影響を与えがちです。そうした状況を改善するために有効なのが従業員サーベイ。社員の声を集めて課題を見可視化し、対策を実行し、その効果を検証する――このプロセスを回すことで、確実に定着率の向上が見込めます。ここでは、サーベイを使った離職率改善の手法をまとめました。
目次
1. 離職が企業にもたらすコストと影響
社員が辞めると、そのたびに求人費やエージェント手数料などの採用コストが増えてしまいます。中途採用なら一人あたり数十万~数百万円が必要な場合も少なくありません。さらに教育や研修に費やした時間と費用も、早期離職が続くほど回収できなくなります。
厚生労働省の「令和5年雇用動向調査結果の概況」(2024年3月)によると、常用労働者の年間離職率は全体で約15%。業種や企業規模によっては20%以上になるケースもあります。新卒だけを見ると、3年以内の離職率は高卒で38.4%、大卒で34.9%(2024年1月公表)に上り、中小企業ほどその負担が深刻です。
また、長年活躍していた社員が辞めると、ノウハウや人脈が失われ、職場のモチベーションや顧客関係にも悪影響が及びます。離職率の高さは企業全体の成長力を損ねるリスクにもなるため、定着率の向上はコスト削減と組織強化の両面から重要な課題といえます。
2. サーベイのメリットと改善プロセス全体像
サーベイの大きな利点は、匿名性を確保したうえで社員の本音を収集できる点です。上司や同僚の目を気にせず意見を伝えられるため、面談だけでは見えにくい不満や要望が浮上しやすくなります。そこで得た定量・定性データを分析することで、離職リスクの原因を客観的に把握しやすくなるのが特徴です。
近年は、従業員のエンゲージメントを数値化し開示する流れが進んでおり、内閣官房の『人的資本可視化指針』(2022年8月)でも重要性が示されています。サーベイは、こうしたエンゲージメントを可視化し、具体的な改善策に結びつけるうえでも役立ちます。
実施から改善までの流れはシンプルです。まずサーベイを行い、結果を分析し、そこから仮説を立てて対策を企画・実施。その後、一定期間をおいて再度サーベイや離職率を確認し、効果を測定します。このサイクルを継続することで、離職率はもちろん、社員のモチベーションや組織文化の改善にもつながります。
3. すぐに使える従業員サーベイの質問例
サーベイを作るときは「何を知りたいか」を明確にしておかないと、分析に困る場合があります。以下は多くの企業で使いやすい質問例です。回答は「非常に満足~不満」などの段階評価に加え、自由記述も入れると具体的な声が集まりやすくなります。
- 職場の人間関係やコミュニケーションに満足していますか?
- キャリアパスや昇進制度はわかりやすいと感じますか?
- 評価の基準や昇給のルールに納得感はありますか?
- 給与や福利厚生で改善してほしい点は何ですか?
- ワークライフバランスは取りやすいですか?不満があれば教えてください。
- 会社のビジョンや経営方針を、どの程度理解・共感していますか?
また、サーベイの目的と回答の匿名性をしっかり伝えておくことも大切です。社員に「結果をどう活かすのか」を明示すると、より正直な回答を得やすくなります。
4. 分析と原因仮説の立て方
サーベイ結果が集まったら、全体傾向を確認すると同時に、部署・役職・年齢・勤続年数などの切り口で深堀りしてみましょう。たとえば、若手は「キャリアパスへの不満」が多い一方、中堅は「評価制度」が不満というように、属性によって課題は変わります。
数字だけでなく、自由記述欄の意見も見逃せません。「ここが離職のネックかもしれない」という仮説を立て、その対策が現場に適用できるか検討することで、施策の優先順位を付けやすくなります。
5. 経営層や管理職の巻き込み方
サーベイで原因が見えても、経営層や管理職が動かなければ対策は進みません。まずは結果を共有し、「離職がもたらすコストとリスク」を具体的に示しましょう。たとえば、新卒社員が1年以内に辞めると、採用費や研修費だけで数十万~数百万円がかかり、職場全体の士気にも影響することを数字で伝えます。
また、対策を立てる段階から経営層や管理職を巻き込み、各現場の事情や意見を反映させると、自発的な協力を得やすくなります。トップダウンとボトムアップの両面から動ける仕組みを作ることで、離職防止に全社的に取り組む文化が育ちやすくなるでしょう。
6. よくある離職原因と対策事例
厚生労働省の調査(2024年1月公表)では、宿泊・飲食サービス業などで新卒3年以内離職率が50~60%を超えるなど、業種によって離職率が高止まりしています。特に規模が小さいほどリスクが高く、人間関係や待遇、キャリアの不透明感など原因はさまざま。ここでは、代表的な原因と対策を具体的に見ていきましょう。
6.1. 人間関係が原因の場合
社内の人間関係が合わずに辞めたいと感じる社員は少なくありません。対策としては、上司と部下の1on1面談を定期的に実施したり、管理職向けのマネジメント研修を行ったり、部署横断プロジェクトを増やすなどが考えられます。人間関係が改善すると、職場に居続けたいと思う社員の割合は大きく上がります。
6.2. キャリアパスが原因の場合
将来像がはっきりしないと、特に若手や中堅社員は不安を抱きやすくなります。ジョブローテーションや社内公募制度などで、部署を超えたキャリア形成の機会を増やすと「ここで成長できそう」と感じてもらいやすくなるでしょう。定期的にキャリア面談を行うだけでも、離職を踏みとどまるケースは多いです。
社員のスキル習得を認定する社内資格制度なども、キャリアパスを明確にするうえで有効です。詳しくは以下の記事をご覧ください。
社内資格制度の作り方と運用のポイント
6.3. 評価制度が原因の場合
評価基準や昇給ルールが曖昧だと、「不公平」と感じる社員が増えます。サーベイでこうした不満が多い場合は、評価項目や基準を社員に開示し、評価面談で具体的なフィードバックを行う仕組みづくりが必要です。管理職の判断プロセスが不透明だと、さらに不満が募る点にも注意しましょう。
6.4. 給与・報酬が原因の場合
給与や報酬制度に不満が多いときは、業界や地域の水準と照らし合わせて昇給・手当の仕組みを見直しましょう。大手企業との差が大きいなら、インセンティブや福利厚生でカバーできないか検討する方法もあります。評価基準と連動させれば、社員のモチベーション向上にもつながります。
6.5. ワークライフバランスが原因の場合
長時間労働や休暇の取りづらさが続くと、離職率は高まりやすくなります。どの部署が忙しいか、残業がどの程度発生しているかなどをサーベイ結果と合わせて分析し、リモートワークやフレックス制度、休暇取得の促進など柔軟な働き方を検討しましょう。仕事とプライベートの両立を支援する環境づくりが重要です。
7. 成功事例とよくある失敗ポイント
ある中堅IT企業では、毎月の簡易サーベイと四半期ごとの評価面談をセットで運用し、1年で離職率を10ポイント下げました。経営層が社員からの改善要望に素早く対応し、上司が面談で成長や貢献度を具体的に伝えたことで、やりがいと将来の見通しが高まったそうです。
一方、サーベイを行っても結果を活かさず、何も変わらないまま終わってしまうケースも散見されます。社員がせっかく本音を伝えても、経営層や管理職が動かないと「ただアンケートを取っただけ」と逆効果になる可能性がある点に注意が必要です。
8. 対策の実行と効果測定
施策を立てたら、現場でしっかり運用し、定期的に効果を検証しましょう。導入から半年後や1年後にサーベイを再度実施し、離職率の変化を追いかけて「どこが改善し、どこが残っているか」を把握します。期待したほど効果がなければ、仮説や対策を見直し、再度サーベイや面談を行う――このPDCAサイクルを回すことで、離職率の低減はもちろん、組織全体の課題把握・改善速度も大幅に向上します。
9. まとめと次のアクション
定着率を高めることは、長期的に見ると採用コストの削減や組織力の強化につながります。社員が安心して働ける環境を整えれば、離職率が下がり、企業成長の速度も上がりやすくなります。
最初は小規模なアンケートや簡易サーベイからでも十分効果があります。結果をしっかり分析して仮説を立て、対策を実行し、再度測定する――この流れを粘り強く続けることが大切です。社員の声を大切にし、早め早めに手を打つ姿勢を示せば、社内の信頼関係と雰囲気も変わっていくでしょう。
厚生労働省の調査(令和5年雇用動向調査結果の概況)によると、年間離職率の全産業平均は約15%。まずは自社の離職率を把握し、サーベイで課題を可視化することから始めてみてください。分析と対策のサイクルを回すことで、定着率だけでなくモチベーション向上や企業全体の成長にもつながっていくはずです。