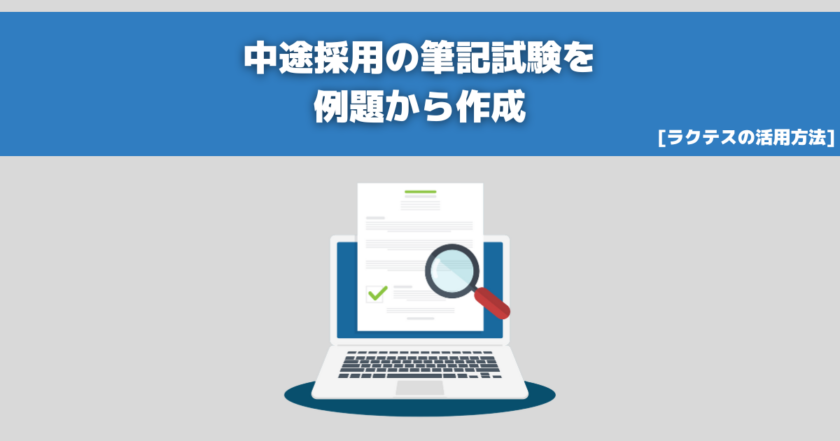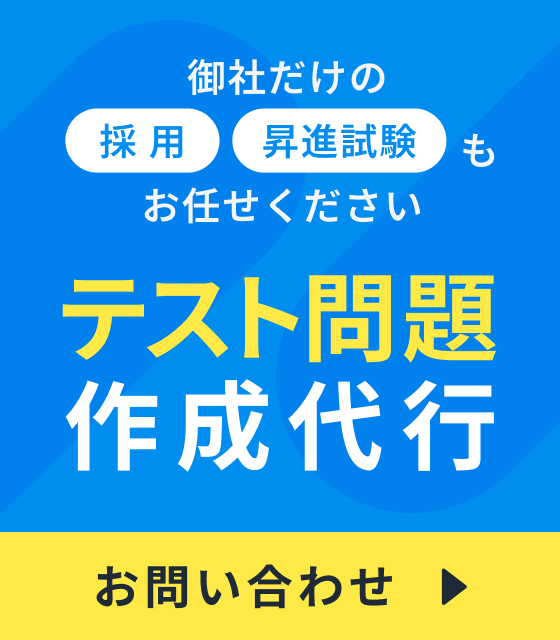履歴書・職務経歴書と面接結果だけを参照して採用すると、具体的な役職に必要なスキルや知識が不足している可能性があります。そのため、独自の中途採用試験の作成をすることを推奨しております。
適性検査では基礎能力や性格的な傾向を見るために実施されることが多く、具体的なスキルセットを評価するのは難しいです。また、多くの企業で同じ内容で実施されますが、事業内容やカルチャーなどによって活躍できる人材は異なります。優秀さは環境によって決まるためです。ある会社ではあまり活躍できていなかった人材が、転職した結果すごく成果が出るということは起こりえます。そのため、自社独自の採用基準を明確にし、それにあわせた筆記試験を実施することがおすすめです。
この記事ではオリジナルの中途採用試験を作成、運用する一通りの流れを解説しています。自社と相性の良い人を効率的に採用するための参考にしてください。
目次
中途採用試験の作成・運用のステップ
1. 採用したい人材像の定義
自社で活躍している人はどのような人たちなのかを整理します。マインドセットや人間関係の構築方法など性格的な傾向から、職種ごとに異なる必要なスキルセットや姿勢など、言語化していきます。ポジションごとに求められる適性、スキル、知識、経験などをドキュメントに整理します。
求人票を作るときにこうした作業は済ませている企業様も多いです。
2.試験の目的設定
次に、リストアップしたスキルなどから、どの部分を筆記試験で確認し、どの部分は面接で確認するのかを分類していきます。筆記試験で確認するのに適している範囲とそうではない範囲があります。
また、筆記試験の中でも、選択式の設問だけでスキルや知識を確認できる範囲と、作文・小論文のような形式でないと確認できない範囲があります。
3. 試験形式の決定
試験の形式は、選考の進行状況や役職に応じて異なります。以下のような形式があります。
- 知識を問う選択式問題:一般的な知識や基本的なスキルを確認するためのものです。正解の明確な問題を出題します。初期段階で実施されることが多いです。
- ケーススタディやワークサンプルテスト:具体的な業務に関連する高度な問題やシナリオを通じて、実際の業務能力を評価します。プレゼンテーション資料作成もしくは小論文のような形式で、これは最終面接前など、選考の後半で実施するのが効果的です。
4. 試験の回数や実施タイミングの設計
選考の進行状況に合わせて、適切な採用試験を設計します。何回試験を実施するのか、役職ごとに内容やタイミングをどう変えるのかなどを考えます。
たとえば、管理職を採用しようとしているのに初期段階で簡単な選択式の問題を実施するのは、候補者にマイナスイメージを与えてしまい、途中で選考を辞退されてしまう要因になりかねません。
また、小論文やプレゼン資料の作成などの作業量が重めの試験の実施は、カジュアル面談・面接などを通じて関係値を作り入社に前向きになってもらってからがおすすめです。
選考初期
初期の段階では、基本的な知識やスキルを確認するために選択式の適性検査や基礎知識テストを実施します。例えば、プログラマーの採用では基本的なプログラミング知識を問う試験を行います。一次面接の前に実施して、面接するかどうかを見極めるのに試験を使えます。
選考中期
二次面接前後で、実務に関連するケーススタディやワークサンプルテストを実施します。これにより、実際の業務で必要なスキルや問題解決能力を評価します。例えば、営業職では営業シナリオに基づいたプレゼンテーションを行うことが考えられます。
選考後期
最終面接前に、役職ごとの高度なテストを実施します。管理職採用の場合、リーダーシップやマネジメント能力を問う問題を設定します。具体的には、チームマネジメントのケーススタディなどです。
何度も繰り返し試験を実施すると面倒に感じられて辞退されてしまうのでは?と思うかもしれません。試験を面倒に感じて辞退するような候補者の方であれば、そもそも入社していただかないほうが良いと思えるような試験の設計にしましょう。
5. 試験問題の作り方
「2. 試験の目的設定」で検討してリストアップした役職ごとに必要なスキルと知識を元に出題範囲を決めます。例えば、プログラマーにはプログラミング言語の知識やアルゴリズムの理解が必要です。次に、評価したいスキルに応じた問題形式を選びます。選択式問題、記述式問題、小論文、ケーススタディ、実技試験などがあります。
例題を活用
ラクテスには、例題としてサンプルのテスト問題が豊富に登録されています。例題を自由に組み合わせて利用することで、迅速かつ効果的に独自の採用試験を作成できます。
問題のカスタマイズ
例題をベースに、あなたの会社の採用要件に合わせてカスタマイズします。難易度の調整や設問の追加・削除を行い、最適な試験を作成します。採用ペースによりますが、役職ごとに異なる試験を作成することを推奨しています。
参考:ラクテスで人気の中途採用筆記試験に向いている例題
例題を活用して問題を作れることを説明しましたが、中途採用での筆記試験で特によく使われている例題のカテゴリーをいくつか紹介いたします。
論理的思考能力
地頭の良さを計測する目的で論理的思考能力についての問題を出す企業は多いです。中途採用だけではなく新卒採用でも使われることの多い例題です。
論理的思考力と数的処理能力を測るテスト
論理的思考の有無をはかる問題
読解力
文章で指示をすることが増えてきています。他の人が書いたテキストの意図を正しくつかめるかは仕事の効率を左右します。
読解力/文章理解力テスト
国語問題 文章整序 サンプル試験問題
計算・数学・データリテラシー
出題の難易度は会社で求めるレベルによって大きく異なりますが、計算や数学の問題を出すことで、数字で考える力を見ることができます。
計算のスキルチェック・採用試験用のテスト一覧
データ分析基礎・データリテラシーのチェックテスト
財務会計/経理
ある程度以上の役職者には財務諸表を読める知識を求める会社があります。また、経理担当者の採用で仕訳などを理解しているかを確認する意味合いで使われることがあります。
経理職の採用試験向け 簿記・仕訳に関する知識確認テスト
基本的な仕訳スキルをチェックできるテスト問題
ITリテラシー
基本的なパソコン操作やITのスキル・知識は業務効率に直結します。採用する前にどれくらいのITリテラシーがあるかを確認することで、自社業務とのミスマッチを避けることができます。
【初級~上級レベル】Microsoft Excel(エクセル)実務スキルチェックテスト
ワード(Word)のスキルチェックテスト問題
ITリテラシーチェックテスト
専門知識
プログラミング、ネットワーク、Webデザインなどについて、経験者であれば解けるであろう難易度で出すことで、実務経験を確認することができます。入社してから実はまったく期待する業務ができなかったとなると、非常に大きな損害になってしまうため、ミスマッチを減らすために面接前の筆記試験もしくは面接中のワークサンプルテストの実施がおすすめです。
Javaプログラミングに関する基礎知識を測るテスト問題
ネットワーク基礎知識確認テスト
Pythonの基礎知識チェックテスト
Webデザインに関する基礎知識チェックテスト
6. 試験の実施
採用試験を受験してもらうときには、以下のような方法があります。
- 紙で印刷して、オフィスに来社してもらい実施
- デバイスを用意し、ExcelやWordなどで問題を配布して実施
- Google FormsやMicrosoft Formsのようなフォーム作成ツールで実施
- 試験作成・運営の専門ツールのラクテスでオンラインで実施
それぞれメリット・デメリットがありますので自社の状況にあわせて選びましょう。たとえば紙で印刷して実施すると印刷代や採点や集計にかかる作業時間分の人件費などのコストが大きくかかります。デジタル化するのとくらべて、受験者のITリテラシーなどによらず誰でもすぐ直感的に受験できる、受験用のデバイスを用意するといった準備の手間が減る、オフィスに集まって実施することで不正などが発生しにくくなるといったメリットもあります。業務用のパソコンやスマホを普段使う機会の少ない会社では、紙での実施のほうが効率がよいかもしれません。
一方で、デジタル化することによって、事務局対応にかかる時間などは大幅に削減される、採点の間違いがなくなるなどのメリットもあります。
ラクテスを利用すると、問題の作成、受験、採点や集計、データ管理などがすべてクラウド上のツールで完結しますので、中途採用試験の運用にかかわる業務負荷を減らすことができます。
7. 試験の評価
試験結果を履歴書や職務経歴書の内容と関連づけて評価します。一次面接よりも前に試験の結果だけで判断する場合もあれば、面接後に試験を実施して面接の内容を含めて総合的に判断することもあります。
試験結果と職務経歴書に記載された経験が一致しているかを確認します。例えば、プログラミング経験があると記載されている場合、実際のコード試験でそのスキルが証明されるかを見ます。
筆記試験の結果だけでなく、面接での印象や他の評価要素も考慮します。例えば、チームワークやコミュニケーション能力など、筆記試験では判別できないスキルもあります。
8. 結果の見直しと改善
結果の分析
試験の結果を分析し、どの部分が有効だったか、どの部分が改善が必要かを評価します。具体的には、採用後の業務パフォーマンスと試験結果の関連性を見ます。
改善策の実行
見直しの結果を基に、試験の内容や評価基準を改善します。技術や業界の変化に対応するため、定期的な見直しと更新を行います。
中途採用試験を作成するためのステップを紹介しました。会社の成長に貢献する優秀な人材を見つけ出すために、試験の内容はもちろん、運用や選考プロセスも含めた見直しを継続していくことが大切です。
ラクテスは、中途採用試験の作成や運用を効率化できるツールです。無料のプランがございますので、ぜひ以下からご登録いただいてお試しください。
採用試験・テストの作成と運営を簡単に | ラクテス